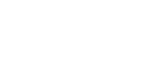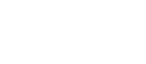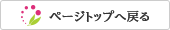ページの本文です。
ゼミの紹介
2025年4月1日更新
西村純子ゼミ(家族社会学演習)
家族にかかわる現象について、社会学的な視点から考えます。家族社会学や社会学の入門的なテキストを頼りに、家族にかかわる現象を社会学的にとらえるときの理論や概念、方法論を学ぶとともに、実際に起こっている現象について、どのような見方ができるかを、ディスカッションを通して考えます。ゼミでは、意見を自由に出しあいながら、新たな見方・考え方を発見するプロセスを重視したいと考えています。
脇田彩ゼミ(生活福祉学演習)
ジェンダーと労働・生活・福祉・社会階層に関わる問題について、社会学の視点から、社会調査によるデータにも依拠しながら考えます。文献講読によって、ジェンダーと労働・生活・福祉・社会階層についての基礎知識を身につけ、その知識を現代社会の事象を読み解き、議論するために用いて、考えを深めていきたいと思います。また、文献やデータを複数で読み解く経験や、研究報告やコメントを行い、学んだ知識に基づいて積極的な議論を行う力を得てもらいたいと思います。
大森正博ゼミ(消費者経済学演習)
大森ゼミでは、隔年で「公共経済学」、「産業組織論」という学問分野を学ぶことを通じて、経済学の基礎を徹底的に身につけて、現代社会において生じている様々な社会問題について考えています。ゼミの雰囲気は、分からないことがあればとことん話し合うことができ、自由に自分の意見を言い合える雰囲気です。ゼミにおける基礎的学習、訓練と並行して、3年次前半には学園祭での発表を目標にしたグループ研究、他大学とのインターゼミナール、3年次後半からは卒業論文のための研究を行っています。
斎藤悦子ゼミ(生活経済学演習)
このゼミでは次の5つのテーマ、①家計と消費、②生活時間、③ペイドワーク、アンペイドワークのあり方、④家事労働の社会化、⑤生活の協同をとりあげます。前期は、①~⑤のどれかを取り上げ、それに関する理論を学んだり、実態把握を行います。後期は前期で学んだことを踏まえ、実際の生活問題の解決に迫りたいと思っています。何が問題であり、それを解決するにはどうしたらよいか。一緒に解決の方法を様々な視点から検討しましょう。
小谷眞男ゼミ(生活法学演習)
報告も討論も学生中心を徹底。毎回、全参加者が最低一度は発言しないと家に帰れない雰囲気です。最近の年間テーマは「ベッカリーア『犯罪と刑罰』を読む」「死刑存廃論」「家族法の国際比較」「マイノリティと法」「リスク社会・情報化社会における消費者法」「精神医療と市民社会」「ポルタリス『民法典序論』を精読する」「古代ギリシャの刑事裁判「ネアイラ弾劾」を読む」「法と文学」など。テキストを講読したり、自由報告形式を取ったりしながら、法学のさまざまなジャンルを基礎から勉強しています。そのほか、法廷傍聴や児童相談所見学、刑務所・少年院ツアー、国民生活センター訪問などを随時実施。コロナ禍ではイタリアの児童施設や学校をオンライン訪問しました。
デ アウカンタラ マルセロ ゼミ(家族法演習)
ゼミでは、夫婦・親子などの家族関係をテーマとして、法学・政策学の視点からアプローチしています。自分が関心のあるテーマを見つけ、それを掘り下げ、その成果をリサーチペーパーの形にまとめることを目指します。2019年度は、性的マイノリティの家族形成や養子縁組をめぐる諸問題について具体的な事例を検討しながら、全員でディスカッションをしています。
豊福実紀ゼミ(生活政治学演習)
私たちの生活と密接に関わる政治・政策について多角的に学ぶゼミです。政治学についての知識を深めながら、ゼミ生が関心を持ったテーマや時事問題などについてディスカッションを行います。ゼミ生主体で、新しいものの見方に気づく楽しさや、論理的に思考する重要性を実感できるゼミ運営を心がけています。