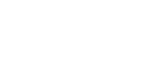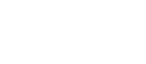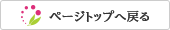ページの本文です。
2021年度シンポジウム
2024年7月1日更新
(詳細は『生活社会科学研究』28号参照)
開催日時:2021年6月12日(土)
I. 生社新任教員、大いに語る「職業威信とジェンダー」
脇田彩(お茶の水女子大学基幹研究院助教)
新任教員の脇田が「職業威信とジェンダー」というタイトルで、研究を紹介しました。職業威信は階層研究における社会的地位の重要な指標の1 つとされているもので、人々による職業への社会的評価に近いものです。職業威信スコアが、その職業に就いている人の性別によって異なるのか、異なるとしたらどのように、なぜ異なっているのかといったことを研究した結果を、2020年に実施した調査の方法とともに示しました。これまでの研究により、多くの職業の職業威信スコアの平均値に男女差があるということはなく、しかし、その職業における多数派が少数派よりも高い職業威信スコアを得る傾向にあることが分かりました。具体的に言うと、男性が多い職業では男性の職業威信スコアが、女性が多い職業では女性の職業威信スコアが高いということです。さらに、この傾向は、各職業について、男性向き・女性向というジェンダー・ステレオタイプが持たれていることによって生じることが示唆されました。ただし、たとえば一部の管理職について、男性の方がよく就く職業であるにもかかわらず、女性の方が男性よりも高い職業威信スコアを得るといった、さらなる説明を必要とする結果も得られました。最後に、ジェンダーによる格差を考えるとき、なぜ女性は高く評価されている社会的位置・領域に行けないのかという側面を論じるだけではなく、女性がいる位置・領域、女性が行ってきた活動はなぜ高く評価されないのか、大きな報酬を得られないのかという側面からも研究することが必要ではないかと論じました。
II. パネルディスカッション「学生と考える、パンデミック下の学生の意識と行動」
脇田彩(お茶の水女子大学基幹研究院助教)
河上美紀・菅沼佑梨・谷口佳菜子・中山遼香・藤田真純(お茶の水女子大学生活科学部人間生活学科生活社会科学講座3年生)
2020年度、生活社会科学講座の科目「生活調査法」「生活社会調査実習」において、受講生とTA、教員が実施した「パンデミック下における学生の意識と行動調査」の結果を踏まえて、パンデミックが学生の意識と行動に与えた影響について、担当教員の脇田と受講生の一部によるパネルディスカッションを行いました。この調査は、2020年10月にお茶の水女子大学の学部生332人を対象にオンライン調査として行われ、調査項目にはCOVID-19によるパンデミック初年度の学生生活、社会関係、オンライン授業、パンデミックに関する情報、不安やストレスなどが含まれていました。受講生はそれぞれの問いと仮説に基づいて質問項目を作成し、調査データを分析しました。パネルディスカッションでは、ストレスとソーシャルサポート(河上氏)、オンライン授業の影響(菅沼氏)、就職や仕事に関する意識(谷口氏)、パンデミックの家事や家族への影響(中山氏)、余暇やサークル活動への影響(藤田氏)という5つのテーマについて、それぞれ学生から報告が行われ、相互にコメントし、フロアや担当教員からの質問に答えました。報告では、ソーシャルサポート、とくに情報共有がストレス軽減に重要だったこと、オンライン授業に対する満足度は全般的に高いけれど支援が必要な学生もいたこと、パンデミックによって職業選択に関する意識は変化しなかったこと、学生の間でも家事時間が増えたこと、余暇の過ごし方の変化が学生の満足度を低下させたことなどが示されました。報告とコメントによって、パンデミックが学業、就職活動、アルバイト、サークルを含めた余暇活動、家族など、さまざまな分野の意識と行動に影響していることが明らかになったと言えます。さらに、2020年度の1年生の経験がこれまでにないものであること、パンデミックを契機に見直されたこと、パンデミックの影響の大きさに個人差があること、お茶の水女子大学の特徴などが見えてきました。
学生の感想
Iについて、学生から、「調査法が興味深かった」「男性がケアに関わる職場に参入することは男らしくないとして評価が低いのではないか」「管理職の女性は「女性の社会進出」の象徴として高く評価されるのではないか」「利用者が男性の参入についてよく思わない職業があることが、結果に影響しているのではないか」「他国との比較も見てみたい」「ジェンダー・ステレオタイプにも種類があると思う」「ジェンダー・ステレオタイプの影響がなくなることを願う」といった感想が寄せられました。
IIのパネルディスカッションについては、「身近なテーマについての調査で、調査結果にも納得した」「パンデミックによる社会の変化のうち良い部分についても考え直す機会になった」「座学はオンラインでできたが、留学や研修などの貴重な機会が失われてしまった」「人とつながりがあり、情報共有ができることの重要性を感じた」「授業の合間の友人との議論や雑談によって学びを深める機会がなくなった」「実家暮らしか一人暮らしか、友人がどのくらいいるかによって、パンデミックの影響は違うと思う」「同級生の発表が刺激になった」「自分が回答した調査の結果について聞けて良かった」といった感想が寄せられました。
文責:脇田彩